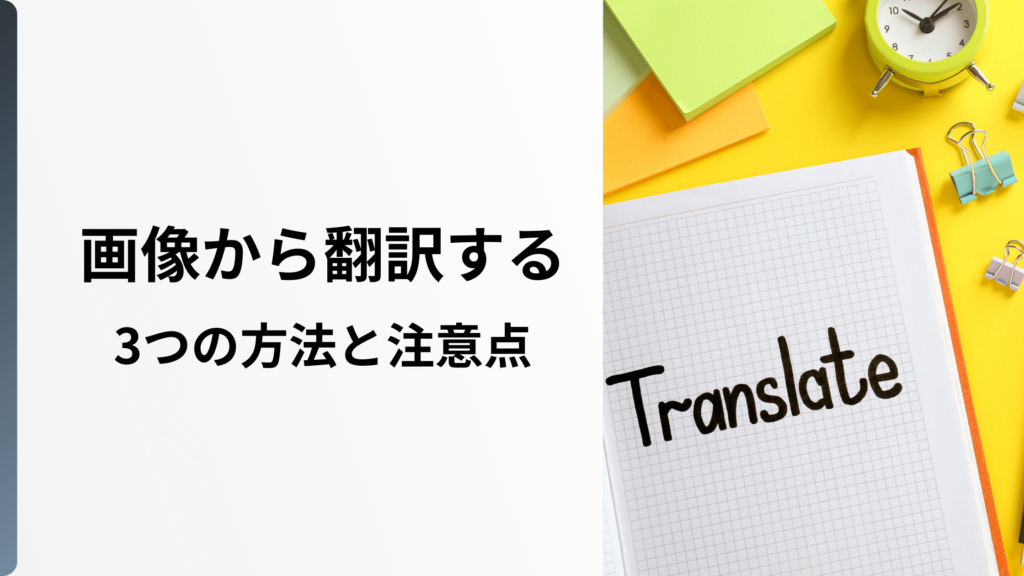この記事の監修者
山田 優(Masaru Yamada)
立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科博士(異文化コミュニケーション学/翻訳通訳学)。フォードモーター社内通訳者、産業翻訳者として活動。その後日本通訳翻訳学会理事と一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会(AAMT)理事を歴任。 詳しく見る
近年、日本を訪れる外国人観光客の数は年々増加しています。観光庁が公表している統計データによると、ここ数年のインバウンド需要は右肩上がりで推移しており、これからも訪日外国人が増えていくことが期待されています(JNTO [1])。
インバウンド需要が回復し、お店に外国人観光客の姿が戻ってきたものの…
「メニューが日本語だけで、何を頼んでいいか分からず困っている…」
「スマートフォンの翻訳アプリを片手に、首をかしげている…」
お客様のそんな姿を見て、もどかしい思いをしたことはありませんか? この記事では、そうした悩みを解決するため、コストを抑えつつ料理の魅力を最大限に伝えるメニュー翻訳の具体的な方法を、実践的なコツと共に詳しく解説します。
そうした状況下で、飲食店のメニューを多言語化して外国人にわかりやすく提供することの重要性が高まってきました。英語や中国語など、海外のお客様が理解しやすい言語でメニューを整備することで「どんな料理なのか」が正確に伝わり、スムーズな注文や満足度の向上につながります。
本記事では、メニューを翻訳する必要性とメリット、具体的な翻訳方法の種類、そしてポストエディット(後編集)を活用したメニュー翻訳の進め方について解説していきます。外国人観光客へのおもてなしを強化し、店舗の評判や売上向上を目指す方はぜひ参考にしてみてください。
メニュー翻訳の必要性とメリット
外国人観光客は日本の食文化に大変興味を持っていることが多いですが、問題になるのが言語の壁です。日本語のメニューが読めず、どんな料理なのかがわからない状態でオーダーするのは不安が伴います。そのため、メニュー翻訳は単に言語を置き換えるだけでなく、観光客の満足度を左右する重要なポイントになっています。
まず、メニューを多言語化することでお店側が得られる効果としては、以下のようなものが挙げられます。
・誤解を防ぎ、料理の特徴を正確に理解してもらえることでクレームが減り、リピーター獲得が期待できる
・外国人観光客が多いエリアや、旅行ガイドブックで紹介されるような店舗の場合、多言語メニューが整備されていることで口コミ評価が高まり、さらなる集客アップを狙うことが可能
・飲食店が対応を整えることで「外国人歓迎」というポジティブな印象を与え、お店全体のブランド価値を高められる
特に日本の食文化は海外でも高い評価を受けており、「日本の味を海外の人にも楽しんでほしい」と考える飲食店オーナーは多いでしょう。そうした思いを現実化するためにも、メニュー翻訳は欠かせない取り組みといえます。
一方で、翻訳精度が低いメニューでは誤解が生じやすく、文化的背景や調理法が正しく伝わらないことがあります。観光庁の「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」でも、直訳ではなく『体験や背景が伝わる表現』を推奨しており(観光庁 [2])、特に飲食関連では料理名や食材の説明を丁寧に補足することが重要です。
メニューを翻訳する際の注意点
多言語メニューを導入する上で重要なのは、外国人観光客がメニューを見て「どのような料理か」「どんな味や特徴があるのか」をイメージしやすい表記にすることです。機械翻訳だけに頼ると大意は伝わっても、料理の背景や細かな味付けが誤解される場合があります。そこで、機械翻訳の訳文をポストエディットで補足することで、注文時のトラブルを大幅に減らすことが可能です。
例えば、焼き鳥を提供している居酒屋で英語メニューに「Yakitori」とだけ記載すると、どの部位が使われているのか曖昧で、海外のお客様にとっては「肉のどの部位を食べるのか」わかりにくいケースがあります。特に、人によっては内臓系好まない方もいるので、きちんと訳してあげることが親切です。
そこで、
「Grilled Chicken Skewers(with various parts such as thigh, breast, etc.)」
訳:焼き鳥(もも肉やむね肉など、さまざまな部位を使用)
と説明を加えれば、部位の違いや調理法が具体的に伝わり、安心感を与えられます。
また、お寿司店など魚がメインの料理を提供する場合は、写真と一緒に英語名・日本語名の両方を併記すると「どの魚で、どんな味がするのか」が直感的に理解しやすくなります。さらに、ポストエディットで魚種名や味わいのポイントを補足すれば、「食べたことのない魚でも試してみたい」という意欲を引き出しやすくなります。
加えて、アレルギーや使用食材の情報を明確に示すことも重要です。特に海外からの旅行者にとって、宗教的制約やアレルギーは命に関わる問題となる場合があります。
消費者庁が示す「食物アレルギー表示に関する情報」では、主要7品目(卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生)を中心に、誰にでも分かるように表示することが推奨されています(消費者庁 [3])。このように、メニュー翻訳の際は単なる文字の置き換えで終わらせず、海外の方の視点で情報を分かりやすく盛り込むことが大切です。
メニュー翻訳の方法
メニュー翻訳の方法は大きく分けて「自動翻訳ツールの活用」「専門翻訳サービスの利用」「機械翻訳+人手を組み合わせた翻訳」という3つのパターンがあります。それぞれの特徴を理解し、店舗の規模や予算、翻訳精度への要求度合いに合わせて選択していくと良いでしょう。
自動翻訳ツールの活用
昨今は翻訳エンジンの性能が向上しており、Google翻訳などといったサービスは短文なら比較的正確な訳を得られるようになっています。無料で使えるため、費用を抑えたい場合に適しています。
ただし、翻訳の品質は元の文章の書き方や料理名などの固有名詞に左右され、直訳や誤訳が発生しがちです。日本特有の食材名や調理法をそのまま自動翻訳すると意味不明な表現になることもあるため、注意が必要です。
専門翻訳サービスの利用
プロの翻訳者や翻訳会社に依頼する方法です。様々な言語ペアを取り扱っているサービスが多数存在します。コストは自動翻訳ツールを使用する場合より高くなりますが、専門知識を持つ翻訳者が対応するため、料理名や食材名のニュアンスが正しく伝わりやすく、文化的背景も踏まえた的確な翻訳が可能です。店舗の看板メニューや独自の料理コンセプトを丁寧に表現したいときに適しています。
機械翻訳+人手を組み合わせたハイブリッド翻訳
機械翻訳を下訳として活用し、最終的に人間の翻訳者が校正・修正を行う手法をポストエディット(後編集)といいます。自動翻訳ツールで下訳を作ることで翻訳の作業時間を短縮しつつ、誤訳や不自然な表現を最終的に取り除くことができるため、費用対効果に優れた選択肢といえます。特にメニューのように文字量が限られた文書の場合、効率よく品質の高い多言語メニューを作成できる可能性が高まります。
一方で、「写真と単語だけで十分」という現実的な判断も
ここまでメニュー翻訳の様々な方法を解説してきましたが、多くの飲食店、特に個人経営のお店では、「正直、そこまでコストも手間もかけられない」と感じるのが本音かもしれません。
「うちは写真付きのメニューだから、簡単な英単語の併記だけで十分伝わる」 「お客様のほとんどは日本人。外国人観光客のために完璧な翻訳を用意するより、その分、食材の質を上げたい」 「下手に翻訳してクレームになるくらいなら、むしろ日本語のままの方が『本物感』があって良い」
このように、店のコンセプトや客層によっては、必ずしも完璧な多言語メニューが最適解とは限りません。写真やジェスチャー、そして片言のコミュニケーションで十分に「おもてなし」が伝わる場面も多く、コストや手間をかけないという判断は、経営者として非常に現実的なものです。
では、どのような場合に、この手軽な対応から一歩進んで、より品質の高い翻訳を検討すべきなのでしょうか。
それは、料理の背景にあるストーリーやこだわり、あるいは日本酒の繊細な味わいの違いといった、言葉でしか伝えられない付加価値を武器に、客単価の向上や、海外の食通からの高い評価を目指す場合です。
以降では、そうした「伝える」ことで価値を高めるための、具体的な翻訳の仕上げ方について解説していきます。
ポストエディットとは
ポストエディットとは、機械翻訳(MT: Machine Translation)によって自動生成された訳文を、人間の翻訳者や校正者がチェックし修正して最終的な翻訳を仕上げる工程のことを指します。近年、機械翻訳の性能は飛躍的に進歩しており、ニューラルネットワークを活用した高度な翻訳エンジンが普及しています。しかし、料理名や各国特有の食材、調理法などについては、文脈や文化的背景を適切に反映できないケースも多いです。
そのため、機械翻訳の訳出結果をそのまま用いると「何となく合っていそうで、実は誤訳している」という問題が起きるリスクがあります。しかし、ポストエディットを挟むことで、そうした機械翻訳の弱点をカバーし、自然で正確な文章に仕上げることができます。機械翻訳が得意とする「大量のテキストを素早く翻訳する」という長所と、人間の翻訳者が持つ「文脈に即した柔軟な表現力」の両方を取り入れられる点が大きなメリットです。
メニュー翻訳におけるポストエディットの実践
ここでは、実際にメニュー翻訳をする際にポストエディットをどのように導入すれば良いのか、その流れや注意点を詳しく解説します。
機械翻訳で一度に大量のメニュー文言を翻訳し、まずは大まかな訳を完成させます。その訳文をベースに、人間の翻訳者やスタッフが不自然な表現や誤訳を修正していきます。この工程では特に料理名や食材名の確認に力を入れるのが重要です。日本独自の料理名の場合、直訳しても海外の方に伝わらない可能性が高いため、料理の特徴や味付けを説明的に書き下すなどの工夫が必要になることもあります。
例えば、居酒屋などで提供される「お通し」は日本独自の習慣ですので、そのまま直訳しても海外の方には意味が伝わりにくいでしょう。(「席料として提供される前菜」といった説明を付け加えることで誤解を防ぎ、サービスの内容をわかりやすく伝えられます。こうした文化的背景や習慣の説明は、機械翻訳だけではカバーしにくい部分です。ポストエディットで細かいニュアンスを補足し、自然な表現になるよう心がけることが大切です。
また、翻訳した内容をネイティブの英語話者にチェックしてもらうことができれば、表現の精度はさらに高まります。もしコストや体制の都合で難しい場合には、複数のバイリンガルスタッフの間でが相互チェックを行ったり、日常的に海外の文化に触れているスタッフの意見を取り入れるなどの工夫でもある程度の品質向上が期待できるでしょう。
ヤラク翻訳で、メニュー翻訳の「面倒」と「不安」を解決する

ポストエディットの重要性は理解できても、「その作業自体が面倒だ」「ツールのセキュリティは本当に大丈夫?」といった不安は残りますよね。
AI翻訳プラットフォーム「ヤラク翻訳」は、そうした飲食店オーナー様の「面倒」と「不安」を解決するために設計されています。
1. 直感的な編集画面で、修正作業の「面倒」をなくす 「ヤラク翻訳」は、翻訳後の文章をチェック・修正しやすい直感的なUIを備えており、パソコンの画面上で原文と訳文を左右に見比べながら編集を進められます。これにより、誤訳や不自然な表現を簡単に見つけ、ストレスなく修正作業を行えます。
2. 鉄壁のセキュリティで、情報漏えいの「不安」を解消する 無料の自動翻訳で懸念される情報漏えいのリスクに対し、「ヤラク翻訳」は法人利用を前提とした強固なセキュリティ体制を構築しています。入力されたデータが二次利用されることは一切なく、お店の秘伝のレシピや新メニューの情報も、安心して翻訳にかけることができます。
3. 「用語集」機能で、こだわりのメニュー名の「ブレ」を防ぐ 「この料理名だけは、この訳文で統一したい」というお店のこだわりを、「用語集」機能がサポートします。一度登録すれば、AIが自動的にその訳語を適用するため、翻訳のたびに修正する手間が省け、メニュー全体で表現の一貫性を保つことができます。

最後に
訪日外国人観光客の増加に伴い、多言語に対応したメニューの整備は飲食店の大きな課題の一つになっています。メニューを翻訳しないままだと「そもそも何が提供されているのか分からない」という問題が生じ、外国人観光客が注文に困るだけでなく、お店側としても大きな機会損失になりかねません。
メニュー翻訳の方法としては、コストを抑えて簡易的に実施できる自動翻訳ツールから、プロに依頼して高品質の翻訳を得る専門翻訳サービス、そして両者のメリットを組み合わせるポストエディットがあります。特にポストエディットは、多言語対応のメニューを効率よく作るうえで非常に有効な手段です。機械翻訳に任せきりにせず、人間の目でチェック・修正を行うことで自然で正確な表現を得られます。
今後も訪日外国人観光客の増加傾向が見込まれる中、メニュー翻訳に力を入れることはお店のイメージアップや売上アップにも直結します。日本ならではの美味しさやおもてなしを、適切に翻訳されたメニューを通じて世界の人々に知ってもらいましょう。そうすることで、海外からのお客様が安心して料理を楽しみ、日本の食文化をより深く理解してくれるはずです。
コピペでそのまま使える【必見!】日本独自の飲食文化の翻訳リスト
メニューを翻訳するときに「これ、どう伝えればいいの?」と悩みがちな表現をまとめました。
よろしければ、お店の翻訳作業にご活用ください!
| 日本語の表現・文化 | 解説(文化的背景) | 英語での説明・翻訳例 |
| お通し | 席料として自動的に出される小皿料理(前菜) | Appetizer served as part of the table charge |
| 食べ放題 | 一定料金で制限時間内に好きなだけ食べられるシステム | All-you-can-eat (buffet-style, within time limit) |
| 飲み放題 | 一定料金でお酒が飲み放題(時間制) | All-you-can-drink (alcoholic beverages, time-limited) |
| 定食 | メイン+ご飯・味噌汁・小鉢などがセットになった和食プレート | Set meal with rice, miso soup, and side dishes |
| おかわり自由 | ご飯や味噌汁などが無料で何度でももらえる | Free refills available (for rice, miso soup, etc.) |
| 焼き鳥の部位 | 部位の名称が文化的に馴染みづらい(例:ぼんじり、せせり、軟骨など) | Specify: Chicken tail, neck meat, cartilage, etc. |
| 味の表現(“さっぱり”“こってり”) | 味の濃さ・油っぽさを表す日本独特の感覚 | Light flavor / Rich and savory flavor |
| 会計時の割り勘 | 支払いを人数で均等に割る文化。海外ではチップ文化が強い国も多い | Bill is split equally among the group (no tipping in Japan) |
| チャージ料 | 席代・サービス料が加算される場合あり | Table charge may apply (customary in some restaurants) |
| 鍋料理 | テーブルで煮て食べるスタイルの日本の料理 | Hot pot dish cooked at the table, shared with the group |
参考文献
[1] 日本政府観光局(JNTO). 「訪日外客統計|月別・年別」. 2025-10-27取得,
https://www.jnto.go.jp/statistics/data/visitors-statistics/
[2] 観光庁. 「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」. 2025-10-27取得,
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/ukeire/kankochi/annaihyoji/shienjigyo.html
[3] 消費者庁. 「食物アレルギー表示に関する情報」. 2025-10-27取得,
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
よく読まれている記事
この記事の執筆者
Yaraku ライティングチーム
翻訳者や自動翻訳研究者、マーケターなどの多種多様な専門分野を持つライターで構成されています。各自の得意分野を「翻訳」のテーマの中に混ぜ合わせ、有益な情報発信に努めています。
よく読まれている記事